Windows11 が22H2からアップデートできていなかったので、手動アップデートした(CF-RZ4)
まぁ、インストール環境に満たないレッツノートに11をインストールしているので、そんなこともあるでしょう。
けど、出来ることなら最新版で使いたいので、調べて忘備録です。
ちなみに、この方法は、要件制限で、Windows11へメジャーアップデートできないPCを、Windows10からWindows11へのメジャーアップデートする手段としても有効な方法です。というか、むしろそっち側で有名な手段っす。ただし、次のメジャーアップデート(25H)では、この方法ができなくなるという情報も!Windows10のパソコンは、早めにしておくべし!
Windows11が22H2からアップデートできなかった悲劇に、一筋の光明が差した。我が愛しのCF-RZ4は、最新のWindows11 24H2への道を閉ざされ、まるで「もう俺、このままでいいんだ…」と諦めかけた中年男性のように、更新の波から取り残されていたのです。インストール環境を満たさないレッツノートに、果敢にもWindows11をインストールした勇者たる私としては、このまま指をくわえて見過ごすわけにはいきません。そこで、私は立ち上がった!この業を背負いし我がPCを救うため、自らの手で運命を切り開く、手動アップデートという名の聖戦に挑んだのです。
まずは、その第一歩。8GB以上のUSBメモリを、我がPCの秘孔へと、ズブリと挿入するのです。まるで、人生を変える重大な決断を下すかのように、いや、それ以上に真剣に、です。
そして、Microsoftの聖地へと巡礼。「Windows 11 のインストール メディアを作成する」という、まるで賢者の書のような、神々しいリンクを今すぐダウンロード。ツールを起動すれば、言語とエディションが問われるので、そこは迷わず次へ。USBフラッシュドライブが選択されているのを確認し、あとはひたすら出来上がるのを待つのみ。この静寂こそが、創造の瞬間なのです。
インストールメディアが完成したら、いざ、最終決戦の地へ!アップデートしたいPCにUSBメモリを差し込み、その存在を認識させるのです。どのドライブ番号に君臨したか(DとかFとか)を心に刻んでおきましょう。
次なるは、黒い画面が支配するプロの領域。「Win + R」でコマンドプロンプトを呼び出し、「Ctrl + Shift + Enter」で管理者権限で起動するのです。このコマンド、ただの起動にあらず。背徳的な許可を得るかのように、指先に力を込め、キーボードを叩きつけるのです。
USBメモリがもしDの戦場に君臨しているのなら、迷わず「d:」と打ち込みエンター。そして、真打登場。「setup /product server」!まさかの「Server」という言葉! 一瞬、あなたは「え?私、今日からサーバーになっちゃうの?」とツッコミを入れたくなるでしょう。だが、恐れるなかれ!これは見かけ倒しのフェイント、Microsoftの遊び心、あるいは神からの啓示、いや、人類の進化を促す壮大な策略に過ぎません。サーバーがインストールされるなどという、野暮な展開は一切ございませんので、ご安心を!
あとはもう、その流れに身をまかせ、運命に全てを委ねるのみ。まるで、人生初の野外プレイに挑戦するかのように、いや、それ以上に大まじめに、画面の指示に従うのです。「Windows Server」の文字が目の前で踊り狂っても、それはあなたの精神力を試すMicrosoftからの愛の鞭だと思って受け止めましょう。
こうして、我が愛機CF-RZ4は、無事24H2という最新の美しさを手に入れ、まるで処女航海を終えた船のように、いや、それ以上に力強く、未来へと羽ばたいていくのでした。めでたし、めでたし。そして、この一連の作業を通して、私は確信しました。人生に必要なのは「夢」でも「仲良し」でもなく、「粘り強い手動アップデート」なのだ、と!
■手順まとめ
8GB以上のUSBメモリをPCへ刺す
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
Windows 11 のインストール メディアを作成する ⇒ 今すぐダウンロード
ツールがダウンロードされるので、ツールを起動 ⇒ 言語とエディションが表示されるので次へ ⇒ USBフラッシュドライブが選択されているので、そのまま次へ
インストール用USBメモリをアップデートしたいPCに刺す
USBメモリが認識しているドライブ番号(DとかFとか)を確認
Win + R
cmd
Ctrl + Shift + Enterで管理者で起動
USBメモリがDで認識されているなら
d:
エンター
続けて
setup /product server
エンター
(serverの文字が表示されると気にせずに)

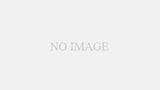
コメント